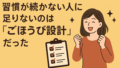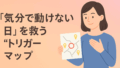「頑張ってるね」が励ましになる日もあれば、
プレッシャーになる日もある。
言葉の温度は、相手の心で決まる。
「頑張ってるね」が届かない理由と、やる気を育てる言葉の選び方
🌱 励ましたつもりが、傷つけていた
「頑張ってるね!」
私は、娘にそう声をかけました。
テスト勉強を頑張っている娘を、励ますつもりで。
でも、娘は黙り込んでしまった。そして、ぽつりと言ったんです。
「お母さん、私のこと見てないよね」
その言葉に、私は言葉を失いました。
「見てるよ。だから、頑張ってるねって…」
「違う。頑張ってるかどうかじゃなくて、私が今どんな気持ちか、わかってないでしょ」
娘は部屋に戻ってしまいました。
私は、励ましたつもりだった。
でも、娘にとっては、「お母さんは私のことをちゃんと見ていない」というメッセージに聞こえていたんです。
なんで・・・?
「褒める」「励ます」ことが良いコミュニケーションじゃなかったの?
私は何が何だかわかりませんでした。
家族にも、友人にも、職場の人にも。
「頑張ってるね!」「すごいね!」「えらいね!」。
そういう言葉をかけることが、相手のやる気を引き出すと信じていた。
何かの本の中で、「褒めることが大事」「ポジティブな言葉を使おう」と書いてあるのを見たことがある。
だから、私も一生懸命、褒めていたんです。
でも、ある日気づきました。私の言葉は、相手に届いていなかった。
「頑張ってるね」と言われた夫は、「まだ足りないってこと?」と疲れた顔をした。
「すごいね」と言われた友人は、「何がすごいの?適当に言ってるでしょ」と冷めた表情をした。
褒めているのに、なぜか相手は嬉しそうじゃない。
むしろ、距離ができる。
そのことに、薄々気づいていたけれど、向き合えていませんでした。
でも、娘の言葉がきっかけで、やっと理解したんです。
私は「伝えていた」けれど、「伝わって」いなかった。
それから、私は言葉の選び方を見直しました。
「褒める」から「気づく」へ。
「励ます」から「受け取る」へ。
その変化が、家族や周りの人との関係を、少しずつ変えていったんです。
💡 気づき:言葉の「方向」を変えるだけで、伝わり方が変わる
振り返ってみると、私はずっと「上から下への言葉」を使っていました。
「頑張ってるね」「すごいね」「えらいね」。
これらは全て、評価する言葉。
私が相手を見て、判定して、褒める。
その構造が、言葉の中に含まれていたんです。
そして、ある日気づきました。
評価される言葉は、プレッシャーになる。
「頑張ってるね」と言われると、「もっと頑張らなきゃ」と思う。
「すごいね」と言われると、「次もすごくなきゃ」と思う。
褒められることで、相手は「期待に応えなきゃ」というプレッシャーを感じてしまうんです。
そして、もう一つ。
評価の言葉は、「見てない」というメッセージになる。
「頑張ってるね」は、結果や行動だけを見ている言葉。
でも、その裏にある気持ち、プロセス、葛藤は見ていない。
だから、言われた方は「表面しか見てくれていない」と感じてしまう。
では、どうすればいいのか。
言葉の「方向」を変える。
上から下への評価ではなく、横に並んで一緒に見る。
「褒める」のではなく、「気づいたことを共有する」。
その方向転換が、言葉を「届くもの」に変えてくれるんです。
たとえば、
- 「頑張ってるね」→「最近、毎日続けてるね。何か変化あった?」
- 「すごいね」→「この部分、工夫したんだね。どうやったの?」
- 「えらいね」→「これ、大変だったんじゃない?」
評価ではなく、気づき。
判定ではなく、共有。
その言葉の方向転換が、相手に「見てもらえている」という安心感を与えるんです。
自己啓発本には、「褒めよう」「ポジティブな言葉を使おう」と書いてある。
でも本当に必要だったのは、「評価する言葉」から「寄り添う言葉」への転換だったんです。
🧠 心理学的解説:「承認」より「心理的安全性」が人を動かす
「褒めることが大事」というのは、一見正しそうです。
でも、心理学では、もっと深い真実があるんです。
まず、心理学者マズローの「承認欲求(need for esteem)」。
人は、他者から認められたいという欲求を持っている。
だから、褒められると嬉しい。これは確かです。
でも、問題は「どんな承認か」。
表面的な褒め言葉は、逆効果になることがあります。
なぜなら、それは「条件付きの承認」だから。
「頑張っているから、認める」「すごいから、価値がある」。
そう聞こえてしまうと、「頑張らなければ、認めてもらえない」というプレッシャーになるんです。
心理学者のカール・ロジャーズは、「無条件の肯定的配慮(unconditional positive regard)」が人を成長させると述べています。
これは、結果や行動に関係なく、その人の存在そのものを認めること。
「頑張っているから」ではなく、「あなたがいるから」という承認。
そして、近年注目されているのが、ハーバード大学のエイミー・エドモンドソンが提唱した「心理的安全性(psychological safety)」という概念です。
心理的安全性とは、「自分がありのままでいても、否定されない」という安心感。
この安全性が高い環境では、人は失敗を恐れず挑戦し、創造性を発揮し、成長する。
逆に、心理的安全性が低い環境では、人は評価を恐れて、失敗しないことを最優先する。
そして、チャレンジしなくなり、成長が止まるんです。
「頑張ってるね」という言葉は、一見ポジティブ。
でも、裏には「頑張っていなければダメ」というメッセージが含まれている。
だから、心理的安全性を下げてしまうことがあるんです。
では、どんな言葉が心理的安全性を高めるのか。
それは、「気づきを共有する言葉」。
「最近、毎日続けてるね」「この部分、工夫してるね」「大変そうだったね」
こういう言葉は、評価ではなく、観察。
「あなたのことを見ているよ」「気づいているよ」というメッセージ。
そして、それに加えて「あなたがいてくれて助かる」という感謝の言葉。
これは、存在そのものへの承認。
結果や行動ではなく、その人がそこにいることへの感謝。
この二つの言葉が、心理的安全性を高め、人を本当の意味で動かすんです。
私自身、この理論を知ったとき、「だから私の言葉は届かなかったんだ」と納得しました。
褒めることで、評価していた。
でも、相手が求めていたのは、評価じゃなく、「見てもらえている」という安心感だったんです。
🌿 実践法:やる気を育てる「3ステップの言葉の選び方」
では、具体的にどんな言葉を選べばいいのか。
私が実践して効果があった、3つのステップをお伝えします。
大事なのは、「言おうとする」のではなく、「感じたことを伝える」こと。
作られた言葉ではなく、本当に気づいたことを共有する。その真実さが、相手の心に届きます。
🌤 ステップ①:「気づく」— 相手の具体的な行動や変化に目を向ける
まず最初に、相手の具体的な行動や変化に気づく。
「頑張ってる」という抽象的な評価ではなく、「何をしているか」「どう変わったか」という具体的な事実に目を向けます。
例:
- 「最近、毎朝早く起きてるね」
- 「この資料、わかりやすくまとめてくれたね」
- 「今日は笑顔が多いね」
- 「この部分、前より丁寧になってるね」
ポイントは、評価語を使わないこと。
「すごい」「えらい」「上手」ではなく、ただ事実を述べる。
この「気づき」の言葉が、相手に「見てもらえている」という安心感を与えるんです。
私の失敗例:
最初、「気づく」をやってみたとき、「早起きしててすごいね!」と言ってしまいました。
これは、気づきではなく、評価。
今は、「最近、毎朝6時に起きてるね。何か変化あった?」と、事実+質問にしています。
すると、相手は「実は、朝の時間が好きになってきて…」と話してくれるんです。
🌿 ステップ②:「受け取る」— 相手の気持ちや努力を想像して言葉にする
次に、相手の気持ちや、裏にある努力を想像して、言葉にする。
結果だけでなく、そこに至るまでのプロセス、感情、苦労。
それを想像して、「大変だったんじゃない?」「嬉しかったでしょ?」と伝える。
例:
- 「毎日続けるの、大変じゃなかった?」
- 「これ、時間かかったでしょ?」
- 「うまくいって、ホッとしたんじゃない?」
- 「途中で諦めそうになったこともあった?」
この言葉は、相手の内面を見ようとする姿勢を示します。
そして、その姿勢が、相手に「わかってもらえている」という安心感を与えるんです。
心理学では、これを「共感的理解(empathic understanding)」と呼びます。相手の立場に立って、その人の世界を理解しようとすること。その姿勢が、信頼関係を生むんです。
私の体験:
ある日、夫が資料を作っていました。
私は「これ、時間かかったでしょ?お疲れさま」と声をかけました。
すると、夫は「そうなんだよ!3時間もかかった」と、プロセスを話してくれた。
そして、「気づいてくれて嬉しい」と言ってくれたんです。
結果を褒めるより、プロセスに気づくことの方が、響くんだと実感しました。
🌼 ステップ③:「伝える」— 「あなたがいてくれて助かった」と存在への感謝を伝える
最後に、存在そのものへの感謝を伝える。
「頑張ったから」ではなく、「あなたがいてくれるから」。
結果や行動ではなく、その人がそこにいることへの感謝。
例:
- 「あなたがいてくれて、本当に助かってる」
- 「あなたがいるから、安心する」
- 「あなたの存在が、私を支えてくれてる」
- 「あなたがいてくれて、嬉しい」
この言葉が、無条件の承認を伝えます。
「何かをしたから」ではなく、「あなたがいるから」。
その無条件の承認が、相手の心を満たし、やる気を育てるんです。
ポイント:
「ありがとう」ではなく、「あなたがいて助かった」。
「ありがとう」は、行動への感謝。
でも、「あなたがいて助かった」は、存在への感謝。
この違いが、伝わり方を大きく変えます。
私の体験:
ある日、娘に「あなたがいてくれるだけで、お母さんは幸せだよ」と伝えました。
娘は最初、照れていましたが、後で「あの言葉、嬉しかった」と言ってくれたんです。
「頑張ってるね」と言っていた頃には、見られなかった笑顔でした。
🌈 まとめ:「褒める」より「気づきを共有する」言葉が人を動かす
以前の私は、「褒めることが良いコミュニケーション」だと思っていました。
だから、「頑張ってるね」「すごいね」「えらいね」と、一生懸命褒めていた。
でも、その言葉は届いていなかった。
むしろ、相手を評価し、プレッシャーを与えていたんです。
でも今はわかります。
人を本当に動かすのは、「褒める」言葉ではなく、「気づきを共有する」言葉。
「最近、毎日続けてるね」「大変だったんじゃない?」「あなたがいてくれて助かってる」
こういう言葉は、評価ではなく、観察。
上から下への言葉ではなく、横に並んで一緒に見る言葉。
その言葉が、相手に「見てもらえている」「わかってもらえている」という安心感を与える。
そして、その安心感こそが、人を本当の意味で動かす力になるんです。
自己啓発本には、「褒めよう」「ポジティブな言葉を使おう」と書いてある。
でも本当に必要だったのは、「評価する」から「寄り添う」への転換だったんです。
言葉の方向を変えることで、家族との関係が変わりました。
友人との会話が深まりました。
職場の雰囲気が温かくなりました。
そして、何より、相手の笑顔が増えたんです。
🌸 40代だからこそ:伝えるより寄り添う力が信頼を生む
40代になって、私は気づきました。
若い頃は、「正しいことを言う」「的確なアドバイスをする」ことが良いコミュニケーションだと思っていました。
だから、相手を評価し、褒め、指導する。
それが、年長者の役割だと信じていたんです。
でも、40代になった今、伝えるより寄り添う力が、信頼を生むと気づきました。
正しいことを言うより、相手の気持ちに気づく。
アドバイスするより、プロセスを見守る。評価するより、存在を認める。
それが、40代のコミュニケーション力だと思うんです。
心理学者のエリクソンは、中年期を「世代性(generativity)」の時期と呼びました。
これは、次世代を育てる時期。
でも、育てるとは、教えることじゃない。
寄り添い、見守り、安心感を与えること。
40代の私たちは、もう「正しさ」を証明する必要はない。
若い人や家族に、「評価する人」ではなく、「安心できる人」として存在する。
それが、40代の役割だと思うんです。
私自身、40代になってから、言葉の選び方が変わりました。
若い頃は、「これが正しい」「こうすべき」と言っていた。
でも今は、「そうだったんだね」「大変だったね」と、ただ受け止める。
その変化が、家族や周りの人との信頼関係を深めてくれました。
それが、40代の成長だと思います。
🌿 続けるためのコツ
「寄り添う言葉」を続けるために、いくつかのコツをお伝えします。
1. 「すごい」を封印してみる
一週間だけでいい。
「すごい」「えらい」という評価語を使わないチャレンジをしてみる。
すると、自然と「気づきの言葉」を探すようになります。
2. 相手の話を遮らない
相手が話しているとき、「でもね」「それはね」とアドバイスしたくなる。
でも、グッと我慢。最後まで聴く。そして、「そうだったんだね」と受け止める。
それだけで、相手は「わかってもらえた」と感じます。
3. 「あなたがいて助かった」を週に1回言う
家族、友人、同僚。誰か1人に、週に1回でいいから、「あなたがいてくれて助かってる」と伝える。
最初は照れるかもしれないけれど、伝えることで、自分の気持ちも変わっていきます。
4. 完璧を目指さない
つい「頑張ってるね」と言ってしまうこともあります。
それでいい。気づいたら、「ごめん、言い直すね。最近、毎日続けてるね」と言い直せばいい。
完璧じゃなくても、変わろうとする姿勢が大事です。
5. 自分にも「寄り添う言葉」をかける
他人にだけでなく、自分にも。
「今日もよくやった」ではなく、「今日、これができたね」「疲れてるけど、ここまでやったね」。
自分にも、気づきの言葉をかけてあげてください。
💫 今日の一歩
今日、誰か1人に、「あなたがいてくれて助かってる」と伝えてみてください。
家族でも、友人でも、同僚でも。
「あなたがいてくれて、私は助かってる」
「あなたの存在が、私を支えてくれてる」
照れるかもしれない。
でも、伝えてみてください。
そして、相手の反応を、静かに見守ってください。
人を動かすのは、評価じゃない。
「見てもらえている」という安心感。
「わかってもらえている」という実感。
その安心感を、言葉で贈ってあげてください。
あなたの言葉が、誰かの心を温める。
評価ではなく、気づきを。
褒めるのではなく、寄り添いを。
今日も、温かい言葉を、大切な人に贈ってください。
その言葉が、明日への力になります。